NEWS
お知らせ
NEWS
- 教育・学生生活
- 教員養成センター
- 入試
- 一般競争契約情報
- 入札
- お知らせ
- イベント
- プレスリリース
- 本学の新型コロナウイルス感染状況
- 受験生の方へ
- 在学生の方へ
- 卒業生の方へ
- 企業の方へ
- 地域・一般 の方へ
- 学務支援システム
- eポートフォリオ
- 調整会のお知らせ
- 保健管理センター
- 教養教育センター
- 鳥取大学学友会
- 鳥取大学好友会
- 鳥取大学は今
- 附属学校部
令和元年7月~9月
2019.10.01
1.「とっとりインターンシップフェスティバル」を開催しました (7月1日)
6月22日、本学をはじめとする鳥取県内の高等教育機関、産業界、自治体で構成する鳥取県インターンシップ推進協議会は、今回で3回目となる「とっとりインターンシップフェスティバル」を鳥取県立鳥取産業体育館で開催しました。同催事は、本学のほか鳥取県内の産官学からなる、地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)「学生と社会の相互交流による人材育成・地元定着推進プログラム」の一環として、同協議会とCOC+、双方の主催により実施したものです。当日は、今夏インターンシップの受入れを行う県内80の事業所がブースを出展し、本学の学生を中心に過去2回を大きく上回る450名の学生が集まりました。開会にあたり、主催者を代表して本学の中島廣光学長が挨拶を述べ、昨今の採用活動の動向を踏まえインターンシップの重要性について触れながら、学生の積極的な参加を呼びかけました。
イベント前半には、「『とっとりインターンシップ』でチャレンジの夏にする!」と題したトークライブが行われ、インターンシップを経験した若手社会人、現役学生等が、低年次からインターンシップに参加する意義や就職活動に活かしたこと、とっとりインターンシップの魅力などについて語りました。トークライブの最後には、インターンシップや鳥取にまつわる全員参加型のクイズ大会があり、会場全体で盛り上がりました。また、平井伸治鳥取県知事から来場者に向けて、熱いメッセージ(代読)が届けられました。
イベント後半に行われた個別企業説明会では、昨年より10社多い企業ブースを精力的に訪れ、メモを取るなどして担当者の説明を真剣に聞く学生たちの姿が見られました。
参加した学生からは、「先輩の経験談を聞けてインターンシップに参加する際の参考になった」「鳥取や県内企業のことをよく知る良い機会となった」といった感想が聞かれました。


2.鳥取県警察から工学部機械物理系学科の西遼佑講師に感謝状が贈呈されました (7月9日)
7月8日、鳥取県警察の佐野裕子本部長から工学部機械物理系学科の西遼佑講師に感謝状が贈呈されました。本件は、鳥取県警察との包括連携協定の中で西講師が行った「鳥取駅前交差点に横断歩道を増設した場合における交通環境への影響」の研究が、鳥取県の安全・安心な社会づくりに大きく貢献したと評価されたものです。今回、西講師はこれまで進めてきた交通流の先進的な研究を、その知見を活かして駅前交差点の車や人の流れを交通や渋滞のもつ特徴や詳細な実データに基づき解析しました。また、本学は地域に根差す大学として地域課題に取り組んできたことが評価され、法人授与を受けました。


3.鳥取銀行寄付講座「マーケティング論」において鳥取銀行平井耕司頭取による講義を行いました (7月17日)
この講義では各分野の第一線で活躍されているスペシャリストを特別講師としてお招きしており、7月11日に行われた講義には、株式会社鳥取銀行代表取締役頭取の平井耕司氏にお話しいただきました。平井氏から、鳥取銀行の概要や現在行っている「空き家対策」「観光振興」等の取り組みについて紹介があり、そのひとつである鳥取産ジビエの活用プロジェクトについては、「鳥取県だけでなく、全国規模のビジネスへ!」という目標が語られました。また、「鳥取銀行は今年で創立70周年を迎える。これからも地元経済や市民のために、まちづくりを支援していきたい」と述べられ、地域を想い、地域を支える企業の姿を見ることができ、学生たちにとって貴重な講義となりました。
全学共通科目 鳥取銀行寄付講座「マーケティング論」とは
本学では、地元経済の発展や地域産業を担う人材の育成を図るため、株式会社鳥取銀行の寄附講座として「マーケティング論」を2007年度から開講しています。本講座は、マーケティング戦略についての基礎的な概念や役割について理解することを目的とし、企業、事業、製品といった各レベルにおけるマーケティング戦略についての身近な企業の事例を取り上げて講義しています。第1クオーターの「マーケティング基礎」では具体的な事例を多く取り上げ、実際の企業のマーケティング活動と理論を結び付けることにより、基礎的な理論やその背景、マーケティング活動について学びます。第2クオーターの「マーケティング実践」では多角化した企業を念頭に置き、そこにおける戦略の階層性を踏まえながら、マーケティング戦略についての基礎的な概念や役割について理解を深めます。


4.朝日新聞「国公立大学進学のすすめ2019」に本学の特集記事が掲載されました (7月30日)
鳥取大学の特集記事が、7月12日付けの朝日新聞朝刊「国公立大学進学のすすめ2019」に掲載されました。また、朝日新聞デジタルの特集ページにも掲載されています。国公立の大学特集2019「鳥取大学」(朝日新聞デジタル)
「世界に貢献する乾燥地研究の拠点」と題して、砂漠化や食糧危機など世界的な乾燥地問題に組織的に取り組む乾燥地研究センター、地域の課題解決から始まり世界を舞台にした研究を行っている本学の強みなどを紹介しています。
また、本学の学生2名が海外留学体験(メキシコ・ウガンダ)について語るなど、本学の魅力が詰まった誌面となっておりますので、是非ご覧ください。

5.探検部の女子ラフティングチームが世界大会で銅メダルを獲得! (8月1日)
本学探検部の女子ラフティングチームが、5月13日から20日にオーストラリア・クイーンズランド州タリー川流域で開催されたラフティング競技の世界大会「IRF2019 World Rafting Championships Turry Australia」に出場し、U-23部門種目別競技の「スラローム」(コース中のゲートを通過していくレース)及び「H2H」(2チームによる直接対決のレース)の2種目で3位(出場チーム数:5チーム)の成績をあげ、銅メダルを獲得しました。「ラフティング」とは、川下りの激流をゴムボートで下るレジャースポーツのことですが、その中でも競技ラフティングはただ川を下るだけでなくタイムを競うレース形式で、種目もスラローム、スプリント、ダウンリバーなどに細分化されています。
探検部は競技ラフティングに力を入れており、2013年には男子チームが同大会に出場し銅メダル2個獲得しており、それ以来の快挙(女子チームとしては本学初)となりました。
6月14日に女子チームの学生3名が結果報告のため学長室を訪問し、リーダーの溝手咲子さん(工学部・3年)は「大会中はうまくいかなかったこともありましたが、大学からの支援のおかげもあり結果を残すことができました。ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えました。

6.2019年度JICA課題別研修「乾燥地における持続的農業のための土地・水資源の適正管理(A)」がスタートしました (8月2日)
今年度で第31回目となるJICA課題別研修「乾燥地における持続的農業のための土地・水資源の適正管理(A)」がスタートしました。本研修では約3カ月間、鳥取大学及び鳥取県内外の各機関で様々な技術研修を実施します。今年度は、アフガニスタン、エジプト、ヨルダン、ケニア、パレスチナ、スーダン、イエメンの7か国から9名の研修員をお迎えし、7月29日に鳥取大学広報センターで開講式を行いました。
中島学長の歓迎の挨拶では、「本研修では、研修員のみなさんが土地資源・水資源の適正管理に必要な知識や技能を身につけ、母国で普及させるために、たくさんの学びの場を準備しています。研修を通して多くを学び、日本文化に触れ、楽しく充実した研修となることを祈念しています」と述べました。
また、開講式に列席いただいたJICA中国センターの田中次長兼研修業務課長からは、「本プログラムは、乾燥地分野で豊富な知識・経験を有する鳥取大学にて実施いただくもので、JICA研修プログラムの中でもアカデミックな内容と実践的な内容が調和した統合的なプログラムです。一旦自国での仕事のことは忘れ、留学したつもりで、他国の参加者と助け合い切磋琢磨して、日本での滞在を有意義なものとしてください」とお言葉をいただきました。

7.令和元年度大学院連合農学研究科学位記授与式を挙行 (9月13日)
9月13日、令和元年度大学院連合農学研究科学位記授与式が挙行されました。平成元年に設立された本研究科は、今年で設立31年目を迎え、これまでに859名の卒業生を輩出しています。授与式では中島廣光学長から学位記が、東政明連合農学研究科長から記念のメダルが一人ひとりに授与されました。
中島学長からは「研究活動を通して磨いてこられた人間力や培ってこられた経験が、みなさまをよりよい将来に導くことを祈念しております」とはなむけの言葉が贈られました。
なお、学位記授与者の内訳は以下のとおりです。
[課程修了] 生物生産科学専攻 4名、生物環境科学専攻 2名、生物資源科学専攻 1名、
国際乾燥地科学専攻 4名
[論文提出] 1名


8.アラブ首長国連邦(UAE)の駐日特命全権大使が本学を表敬訪問しました (9月19日)
9月10日、アラブ首長国連邦(UAE)のカリド・アルアメリ駐日特命全権大使らが、鳥取県訪問の一環として本学に来学し、中島学長を表敬訪問しました。中島学長は、昨年にUAEの国際塩生農業研究センターと本学が学術交流協定を締結したことを紹介し、アルアメリ大使の訪問を機に今後ますますUAEとの交流を深めていきたいと挨拶をしました。また、懇談時には、鳥取県産の新品種の梨「新甘泉(しんかんせん)」と本学が開発に携わった二十世紀梨葉を使用したお茶が振舞われ、大使らは大変興味深くご賞味されました。
表敬訪問の後には、アルアメリ大使から本学学生及び教職員約60名を対象にご講演いただきました。講演では、UAEと日本との関係をはじめ、「多様性と寛容」を大事にする精神がUAE経済発展の原動力となったこと、2020年に中東・アフリカ初の万博「Dubai Expo 2020」が開催されることなどの紹介があり、参加者らとUAEにおける教育等に関する質疑応答が交わされるなど、本学にとっても貴重な機会となりました。
また、午後には石破茂衆議院議員と共に本学乾燥地研究センターを視察され、山中典和センター長からセンターの活動やアリドドーム実験施設等の紹介がありました。アルアメリ大使からは乾燥地での研究内容やUAEとの繋がりについて質問があり、砂漠化対策や乾燥地農業研究についてご理解いただくとともに、本学の人材育成への取り組みにも深い関心を寄せていただきました。
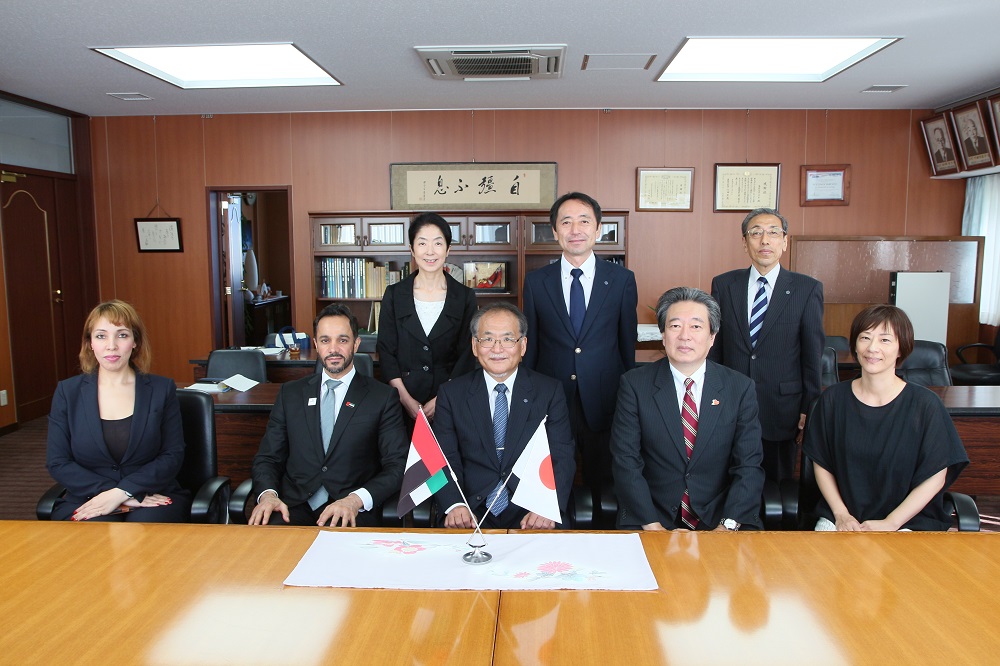


9.持続性社会創生科学研究科学位記授与式を挙行しました (9月25日)
9月24日、本学広報センターにおいて、令和元年度9月修了生にかかる「鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科学位記授与式」を行いました。授与式では、研究科長及び各専攻長の紹介の後、修了生に向けて田村文男研究科長から「サポートしてくれた人たちへの感謝の心を忘れず、本学で得た経験、知識、スキルにより持続性社会創生に貢献するよう願っています」との励ましの言葉が贈られました。
なお、学位記授与者の内訳は以下のとおりです。
[学位記授与者]工学専攻 1名、農学専攻 3名、国際乾燥地科学専攻 5名


10.国連砂漠化対処条約第14回締約国会議(UNCCD/COP14)に参加 (9月26日)
乾燥地研究センター及び国際乾燥地研究教育機構は、9月2日から13日にかけて、インド・ニューデリーにおいて開催された国連砂漠化対処条約第14回締約国会議(UNCCD/COP14)に参加しました。同会議は、1997年にローマで開催された第1回会議後、2年毎を目処に開催されており、締約国政府、国際機関、市民社会団体(CSO)等から多数の関係者が参加しました。
本学からは乾燥地研究センターの恒川篤史教授が政府代表団の一員として参加したほか、乾燥地研究センター及び国際乾燥地研究教育機構所属の研究者と海外連携機関である国際乾燥地農業研究センター(ICARDA)で、「地域密着型の取組みによるレジリエンスと生計の向上(原題:Enhancing Resilience and Livelihoods through Community-based Actions)」と題したサイドイベントを共催し、乾燥地や発展途上国における知識及び技術普及のあり方について、COP参加のUNCCD事務局員、専門家、国際研究機関関係者などとケーススタディの発表や意見交換を行いました。
ICARDAと本学は乾燥地研究のパートナーとして共同研究や学生派遣などを通し関係を深めてきましたが、今回このような国際会議においてサイドイベントを共催したことで、より一層お互いの活動への理解を深めることができました。
今回のCOP14への参加は、わが国唯一の「乾燥地科学」の研究拠点を有する本学にとって、政府関係者、海外研究機関等とのネットワークを更に強化し、国際的プレゼンスを向上させる貴重な契機となりました。


11.マレーシアのマラヤ大学で鳥取大学フェアを開催 (9月27日)
9月11日、国際交流センターは、学術交流協定校であるマレーシアのマラヤ大学において「鳥取大学フェア」を開催し、マラヤ大学の学部生、大学院生、教員等、20名近くが来場しました。本学では、マレーシアマラヤ大学英語研修を、年2回(春・夏)実施しています。この間に、学生交流を中心に協働関係を築き、平成30年2月に全学の「学術交流協定」と「学生交流の覚書」を締結したことにより、この度、両大学のさらなる交流発展のために、鳥取大学フェアを開催する運びとなったものです。
フェアでは、マレーシア政府派遣留学生として鳥取大学工学部を卒業し、フェアのマラヤ大学側の受入れ担当者であるムハマド助教授から、「研究協力の形は様々です。両大学の行っている研究や鳥取での生活等の情報を共有し、今後の交流発展の機会となるよう願っています」と挨拶がありました。
本学からは、工学部の李相錫教授、佐藤昌彦教授、松永忠雄准教授が、鳥取大学と工学部の各専門分野のほか、自身の研究テーマや具体的な技術の活用法について紹介しました。鳥取大学に留学を希望する学生向けの説明では、現在マレーシア政府派遣留学生として本学に在籍している、工学部のNurul Izzah Binti Mohd Kamalさんと地域学部のMarinah Haziqah Binti Hazlanさんが発表を行いました。鳥取は留学生にとって安心して生活できる場所で、大学では学問以外にも、多くのイベントを企画実施しており、日本人学生や地域住民との多くの交流の機会があることを中心に説明しました。
午後からは、マラヤ大学工学部の教員等のプレゼンテーションと、発表内容についての意見交換等が行われ、参加者は終始発表に聞き入り、熱心にメモを取ったり、発表者に内容についての質問を行ったりするなど、活発な交流が行われました。


12.令和元年度医学部公開講座を開催しました (9月30日)
9月7日、21日に、医学部記念講堂において令和元年度医学部公開講座を開催しました。今年度の公開講座は「こころのラボ~発達障害のこと、ストレスマネジメントのこと、考えてみませんか?~」をテーマに、4人の講師が二日間にわたり、発達障害やストレスマネジメントについて講演しました。公開講座には、二日間合わせて総勢250名を超える方に受講していただき、テーマへの関心の高さがうかがえました。参加者からは、「具体的な事例をあげられ理解しやすかった」「身近な問題を色々と学べて良かった」など、大変ご好評をいただきました。
|
講演タイトル |
講師 |
|
発達に遅れや偏りのある子どもの子育て・教育 |
臨床心理学専攻 井上雅彦教授 |
|
活き活きと働くためのストレスマネジメント |
臨床心理学専攻 福崎俊貴講師 |
|
発達が気になる子の診療の実際 |
脳神経小児科 西村洋子助教 |
|
青年期・成人期で初めて気付かれる発達の特性とその影響 |
精神行動医学 兼子幸一教授 |
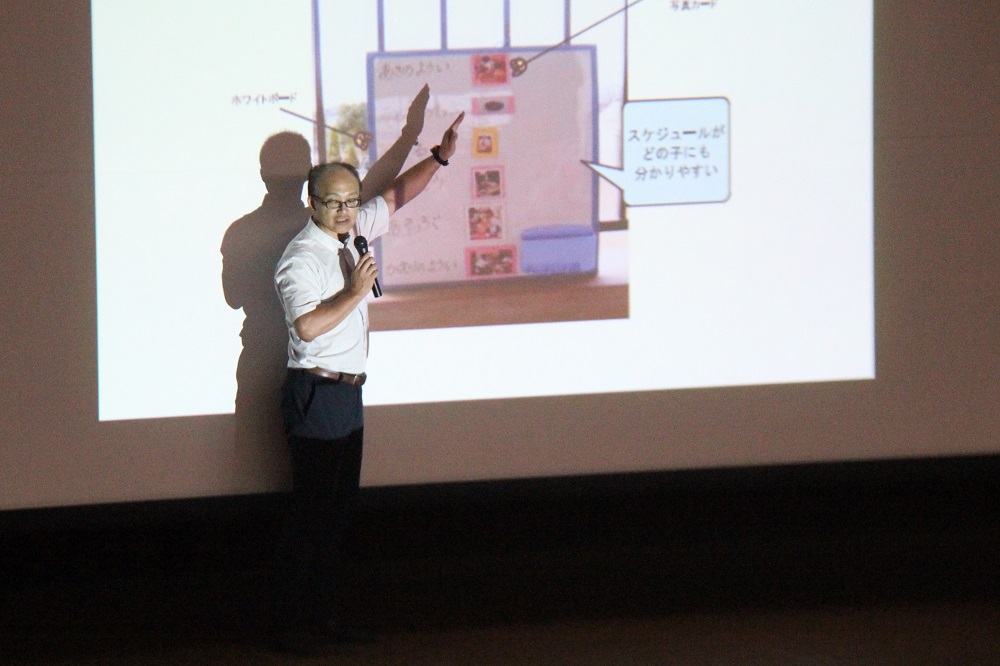

この記事はクローズされました


